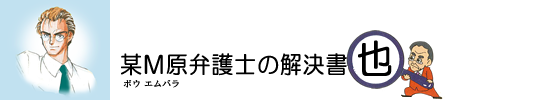
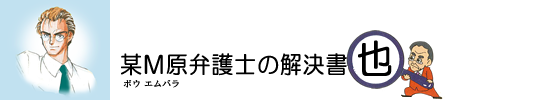
|
Top > 本文
1 求められているのは「より良い解決」
弁護士の取り組む業務は色々ですが、相談者の抱えている悩み事のよりよい解決を求められている点では、どの分野の業務も課題は同じです。
弁護士は、ご相談案件を、よりよく解決する力量を常に問われているのです。
どうしたら良いのか、最初から方向性がはっきりしているご相談もあれば、お話しを聞きながら、あれこれ試行錯誤しながら望ましい解決の姿を見つけ出していくタイプのご相談もあります。
よりよい解決を目指して何はともあれ、相談者の話をじっくりお聞きするところから弁護士の仕事が始まります。
2 「よりよい解決」のため、まず必要なのが聞き取り
口があり、耳があれば、話を聞くことなど、特別の事には思えませんが、弁護士と相談者の関係では、この聞き取りが実に大変なのです。
必要なことを、要領よく聞き出せたら相当なものです。
適切な聞き取りが出来れば、きっと、他のことも相当程度の水準でやりこなせる優秀な弁護士と申せます。それくらい弁護士にとって聞き取り能力は根本的な技能なのです。
ところで、依頼者にとってご自分が重要なことと思って弁護士に話した内容が、解決のためにすべて的を得ているかと言えば、そうではありません。
弁護士も相談者も、望ましい解決のため絶対に押さえておかなければならない重要な事実や事情に、最初は気づいていないことが結構あります。
相談者が抱えている問題を広く深く押さえることは決して簡単ではありません。
相談者と弁護士の会話の目的は、よりよい解決のために押さえておくべき出来事や関連事情を、説明と質問を通して発見していくことにあります。
持ち込まれた問題を弁護士は事案と称しますが、事案の全体像の把握こそ、相談者と弁護士の共同作業で目指すところです。
30分や1時間ではなかなか事案の全容を把握しかねることが実感です。
勿論、短い時間なら、短いなりの聞き取りと助言の仕方もありますが。
さて、出来事のご説明と平行して、依頼者から手持資料のご説明があります。
いつ作成された資料か、誰が作成した資料か、何の目的で作成したのか、いかなる趣旨が読み取れるのか、このようなことを相談者にお聞きしながら弁護士は考えます。
疑問点に気づかず、新たな発見なしに、相談者の手持資料と説明を鵜呑みにして事案の全容をイメージすることは読み誤りの危険を伴います。
相談者の説明を参考材料としながらも、弁護士はもっと深く、もっと完璧に事案を把握したいと願います。
相談者からいただいた情報や資料を縦に並べたり、横に並べたり、あるいは並べ順序を変えてみたりして、何かが見えてこないか、目を凝らし、想像力を働かせて事案の把握に取り組みます。
法律や判例が本格的に検討のテーブルに乗ってくるのは、このようにして事案の把握が出来てからのことです。
弁護士にとって相談者は必要な事実を把握する最大の情報源なのです。だから、みっちりと質問をしてくるはずです。
出来事の掘り下げに熱心で、しつこく質問してくる弁護士は、頼もしい弁護士ですから、とことん質問に答えて、お互いにまだ気づいていない重要な事柄の発見に努めてください。
3 「よりよい解決」に向かっての見通し
弁護士との会話を通じて、望ましい解決の像が見えてきましたら、依頼者は、次のような点についての見通しが欲しくなります。
(1) 私の希望や要求は法的に実現可能でしょうか。
(2) 実現の可能性は何パーセントくらいありますか。
(3) 実現可能であるとしたら、どんな手順を経て、いつ頃、実現するのでしょうか。
(4) 費用はどれくらいかかりますか。
費用のことはきちんとご説明できるとしても、その他のご質問は、明快な回答を差し上げることの大変難しい場合があります。
テレビの人気番組、「○○のできる法律事務所」をご覧になればお分かりのように、弁護士同士で、同じ問題に対する回答が異なることがしばしばです。
ものの見方、考え方、事案に法律を当てはめて答えを導き出す思考過程などが、弁護士により、異なってくるからです。
一つの事案に対する見方、考え方が弁護士を含む法律家全体の間で異なることは大いにあります。三審制度の裁判において地方裁判所の判決が高等裁判所で覆ったり、高等裁判所の判決が最高裁判所で覆り、メディアに報じられることが日常的に見聞されることからも、この点はご理解頂けると思います。
もっとも、見解の分かれ易い案件とそうでない案件とがありますので、毎度、見通しを立てるのが難しい訳ではありませんが。
解決とは望むとおりの決着が実現することですが、果たして本当に実現するだろうかと考えたときに悩ましいことがあります。
例えば、100万円の借用書があるので裁判をすれば100万円を支払えと判決ができることは予測できても、相手は支払ってくれるだろうか、支払えるストックや収入があるだろかといった点に不安が残れば100%の目的達成を相談者に回答することはできません。
また法的紛争の勝敗の見込みを尋ねられて、五分五分と説明されるケースがあります。
しかし見込みが五分五分なら、やってみなければわからないのと同じことなので、見込みを示したことになるのでしょうか。
割合的に説明された勝敗の行方は、そこで示された確率にいろいろな含みがありうるので、そのまま鵜呑みにするのは如何なものかと思います。
五分五分よりも悪い見通しを語れば弱気と思われる心配があり、そうは思われたくないのが人情です。しかし、負けても言い訳しやすく、勝てば、何となく誇らしく説明出来る利点があるかもしれません。
逆に五分五分よりも勝つ見込みの高い見通しを示せば、頼もしく思われ、それは弁護士にとってうれしいことです。その反面、見込み通りに勝って当たり前、万が一、負けてしまえば非難されることが心配です。
こうしてみると、勝敗の行方を、確率的に説明するほかに方法がないとしても、確率を導き出す、いろいろな要素を、丁寧に分析して、相談者にわかりやすく説明す必要があります。
法律家の専門用語をできるだけ少なく、日常の生活感覚に沿って分かり易い言葉でこの説明をしてもらえると大変うれしいです。
時は金なりです。解決までのおおよその所要時間、その間の手順などを紙に書いてくれたら、なお嬉しいです。
4 「よりよい解決」のためには法的思考に閉じこもってばかりでは駄目
(1) 解決方法のいろいろ
よりよい解決を目指して進むコースは次のように色々です。
①裁判所の判決
②判決に行く前に裁判所に間に入ってもらってまとめる和解
③裁判所の調停
④裁判外紛争解決制度の利用(これも色々あります)
⑤裁判所を利用せず弁護士が紛争当事者の代理人となって相手と直接話し合ってする解決
判決は文字どうりの法的解決です。しかし、実は、勝訴判決をもらったからといって、究極的満足を得られない場合もあります。先ほど説明した100万円の貸し金返還の例を思い出して下さい。
判決以外の解決方法は、判決になったらどのような結果になるかを想定しながら、より現実的で柔軟な解決を目指し、時間、労力、費用の節約を重視して採用する解決方法です。
(2) 法的思考にばかり縮こまらない発想
以上のような法的解決とは少し発想を変えた解決もあります。どこでもありそうな不倫の話を例にご説明します。
ア こんなケースがありました
幼稚園と小学校に通う二人の子供をもつ母親が夫の不倫を発見しました。営業マンの夫が、取引先の10歳年上の女性社長と男女の仲になっていたのです。
生活はぎりぎりでやってきた家庭です。離婚して、夫に慰謝料請求しても無駄です。かといって妻はやり直しをする気持ちになれず、また結婚を続けていたところで将来の生活保障になるような甲斐性も誠実味もない夫です。
悔しい思いは抑え切れませんが、さりとて裁判まではしたくありません。
(ア) 女社長から慰謝料をとりたい。
(イ) 夫と女社長の勝手な男女のアバンチュールを今すぐ止めさせたい。
妻の怒りは当然であり慰謝料請求は誠にもっともです。さて、このケースはどのような決着を見たでしょうか。
イ 通常に見られる解決
まず、通常の展開をご紹介します。
事情にもよりますが、この場合、交渉で実現可能な慰謝料額の相場を仮に200万から300万円前後と想定します。
交渉の打ち出しは、女性社長に二度と再び夫と交際しないことを約束させ、金500万円の慰謝料を請求することにします。
相手からいろいろ言い訳や時として妻に対する非難なども出てきます。しかし、不倫の事実は否定できず、訴訟になれば女性社長が慰謝料の支払いを命じられる可能性は高いので、互いにほどほどの落としどころを探すことになります。
しばらく交渉が続いて、女性社長が今後は夫と交際しないと約束し、250万円の慰謝料を支払って解決。
しかし、夫婦の間に信頼関係は回復しません。夫がその後、女性社長と会っているかどうか、妻には確認のしようもありません。先行き、この夫婦の破綻は避けられないように見えてしまいます。
しかし、それでも、弁護士としてその後の夫婦のケアーまですることはできません。仕事はこれで終了です。
以上が法的検討に基づく通常の解決の顛末です。
ウ 法的思考を超えた現実対応の解決
この不倫のケースで、例えば、夫と女性社長が望むなら、離婚して上げるから、その代わり代償として高額な支払いをさせるという発想は如何でしょうか。
こんな夫と結婚生活を続けていても将来の展望が見えてきません。これからも女性問題、生活費問題で絶えずいさかいが起きそうな夫です。夫婦であるだけでも生活防衛になるなら、我慢して結婚生活を続けるという選択肢もありますが、そのような期待さえ持てない夫です。
しかし、だからといって、悔し紛れの離婚で終わらせるのでは能がありません。同じ離婚するなら最大限に高く女性社長に夫を売りつけるという発想です。
不倫をされ、小さな2人の子供を抱えた奥さんの、これからの長い人生を考えたときに、先ほどご説明した正攻法の発想で足りるのか、あるいは捨て身の発想が必要なのかということです。
結果として、このケースの奥さんは夫と離婚することにして、慰謝料ではなく、解決金名目で女性社長から2、000万円の支払いを受けました。女性社長が2000万円を支払ったのは、いうまでもありませんが、今後、不倫相手の男性と天下晴れて堂々と関係を持てるようになった代償なのです。
この解決が果たして良かったのかどうか、それは不倫をされ悩み苦しんだ妻にしかわかりません。
しかし、それにしても、問題の解決にあたり、法律の解釈、運用に長けているだけでは足りず、生活の全体像を掴んで、よりよい解決を想像することが大切なことは確かです。
エ ビジネス上の問題でも同様です
勿論、ビジネス上の問題であっても同様で、会社活動全体の中で問題を捉えながら、直面する事態を解決する発想が大切です。
弁護士は法律の専門家ですから、法律の解釈、運用方法に精通していなければならないのは当然としても、それだけでは不十分です。
よりよい解決を実現するには、会社が抱えた問題に対して、どのような手の打ち方をしたらよいかという広範囲な知恵や、創意工夫が何よりも大切です。
知恵と工夫にヒントを与えるものが法律であり、知恵と工夫を実現する力を与える道具も法律ですが、法律を生かし切るような発想こそが大切ということです。法律に依りながら、法律を超えた、縦横無尽の発想が、相談者に元気を運びます。
5 「よりよい解決」を目指すには勇気も必要
弁護士が依頼を受けて開始する作業は相手のある戦いですから、やってみなければ、どうなるかわからない、という不確実な面がどうしても残ります。
しかし、いろいろ検討してみて、取りかかるべき意義のある案件となれば、先行きに不透明感が残っても権利実現の一歩を踏み出す勇気が必要です。
戦いなしに権利の実現はありません。そして戦いである以上、ゴールまでのすべてが見通せる訳ではありません。
望ましい解決というゴールは、相談者と弁護士が苦労を共にして勝ち取って行くものであり、安全無難なところからは手に入りません。
権利を実現し、思いを遂げるには相談者も弁護士も勇気をもって事に取り組まなければ道は拓けません。
弁護士が根拠のない勇気を発揮し、過剰な共鳴、共感をもって事案に取りかかるのは相談者に対して無責任です。
しかし逆に、慎重、悲観的なタイプの弁護士が、見込み通りにいかなかった場合に相談者から責められることを恐れ、消極的な発言に終始するのも考えものです。
もっとも、このあたりは、言うは易く、行うは難しといったところなのですが。
結局、必要なことは、愚直に一生懸命考えて見通しを立て、手順を整え、やると決めたら果敢に進む事です。
相談者と弁護士が熟慮の上、やるべきだと決めた案件であれば、着手から解決までの間に行われる多種多様な作業と、その間に交わされる人間的交流がベースとなって、相談者と弁護士の間に、いつしか、共通の困難に立ち向かう同志のような感覚が生まれてきます。
このような関係が全ての案件で実現することが理想です。
|