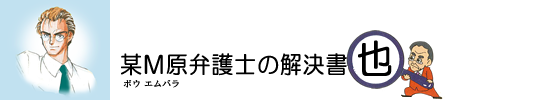
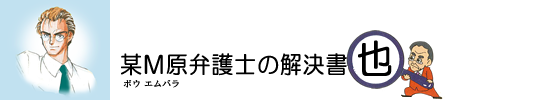
|
Top > 本文
1 はじめに
これまで大変多くの交通事故をめぐる損害賠償請求案件のご相談を受けてきましたが、この分野は検討課題の間口と奥行きが実に広く、深いため、絶えず学習を求められます。
交通事故は絶対に起きて欲しくはないですが、不幸にして起きたときは、せめて車の損傷程度ですんで欲しいと願います。人の怪我を招くような交通事故は、軽傷、重傷にかかわらず辛いものです。
ましてや人命にかかわったり身体障害を残すような重大事故ともなれば、被害者はもとより配偶者や肉親の人生が一変してしまうので、ご本人や身の回りの方々は言うに及ばず、損害賠償問題を担当する弁護士にとっても深刻な事態です。このようなケースでは損害賠償請求にとどまらず、生活防衛を含めた周辺問題にも気を配りご相談にのる必要もでてきます。
2 交通事故の論点の概略
交通事故の損害賠償で通常、論じられる諸問題をざっと見ていきます。
(1) 最初の説明・物件事故報告書
交通事故が起きたら必ず警察に通報して下さい。軽微な事故だからとか、責任をとるから警察には通報しないでくれと相手から頼まれた、などの理由で警察に通報せずにすませてしまう場合がありますが、後日、事故の証明ができないでとても困る事態になりかねません。警察への通報は絶対に行って下さい。
なお、人が怪我をせず車の損傷だけの事故(物損事故)の場合は、かけつけた警察官が事故当事者から事故の様子を聞いて物件事故報告書という簡単な書類を作成します。ここに書かれている内容は、後日、証拠として重要な意味をもってきますので、警察官への事故状況の説明は、是非、きちんと行って下さい。
また、本当は人身事故なのに物損事故扱いにされてしまうケースが時たまありますので、怪我をした場合には人身事故扱いにしてもらうよう警察官にしっかりと注意を促してください。
(2) 事故の様子の記録化
事故はどのようにして起きたのか、まず、これをはっきりさせることがスタートです。とは申しても事故の当事者は、まさか事故が起きるなどとは考えていませんから、事故の様子に関する記憶が曖昧、不正確となるのは当然です。
そこで、どんなに幼稚な絵でもけっこうですから、事故の瞬間から時を巻き戻して、事故にいたる直前の被害者(車)と加害者(車)の動き、走りかた、そして、事故の瞬間までの様子を描いて欲しいのです。
また、道路の車線や幅、センターラインや一時停止線など道路に関する様子、道路周辺の様子、車の流れなど、その他の関連情報も絵の中に描き込んでいただけると大助かりです。
そして以上のことにつき、証拠となる人(目撃者や同乗者等)や物(双方の車についた傷跡等)があれば、しっかり押さえておいて下さい。たとえば双方の車についた傷跡から事故の瞬間にお互いの車が、どのような位置関係にいたのか、どちらのスピードが早かったのか等々、事故の様子を推理することが可能です。是非、双方の車の接触部位や傷の様子が分かるように、事故現場で、事故車の傷が付いた部分の写真を撮っておいて下さい。
(3) 事故の原因・不注意はどちらにあったのか
交通ルール違反や不注意がなければ事故は起きないのが普通ですから、事故が起きれば、誰に、どのような違反があったのか、不注意(過失)があったのかをめぐって議論が戦わされます。この議論を説得的に進めるには先ほど説明したように事故の様子をしっかり押さえておく必要があります。
(4) 過失相殺
ア 過失という考え方
車対車の事故では、信号で停車中に後ろから追突された場合など、ごく限られた事例でしか、相手方に100%の落ち度(過失)がある事故にはなりません。一見、相手がどれほど無謀な運転をしてきたケースでも、その無謀運転に気づいて事故を回避する責任がこちらにも幾分か問われがちなのです。もしかすると、このあたりは事故の被害者の感覚に合わない場合が出てくるかも知れません。
このような考え方の根底には、正しい運転をしていれば落ち度(過失)は問われないというものではなく、車を運転する人は、相手が不注意な走り方をしてくることも念頭において、互いに事故がおきないように出来る限りの注意を払いましょう、という発想があるようです。
例えば、信号が青なので交差点を通過しようとした時に、赤信号を無視して突っ込んできた車に衝突されたケースを考えてみます。常識的には、加害者の不注意(過失)が100%、被害者には落ち度(過失)なしと考えがちです。
しかし、必ずしもそうではありません。青信号で交差点を通過する車の運転者は、万が一赤信号を無視して突っ込んでくる車がないかどうか左右を注意しながら交差点を通過するべきで、前方左右を見ながら走行していれば突っ込んでくる車に気がついて事故を避けることができたと反論がでるようなケースですと、被害者にも僅かですが落ち度が問われる可能性もあります。
事故が起きてしまった後に、自分の正当性を幾ら主張しても、時間を事故の起きる前に戻して怪我や車の損壊を消してしまうことはできません。事故がおきたら後の祭りで取り返しがつきません。ですから、お互いの注意で事故が避けられる余地があるなら、常日頃から、精一杯の注意を払っておくことが安全運転の知恵といえます。
イ 過失割合
事故の原因となった不注意(過失)を100%として、事故当事者双方の過失がそれぞれ何パーセントになるか(双方の過失の合計を100%とします)を評価することを過失相殺といいます。
事故の様子を沢山のパターンに分類し、それぞれの事例における事故当事者双方の過失割合を表にしたものができあがっていて、損害賠償請求の裁判や交渉では権威ある基準として利用されています。
これは不幸な事故によって生じた損害を、事故当事者間で公平に分担しあいましょうという発想ですが、先ほども申しましたように、被害者には納得しにくい場合があります。
(5) 事故によって生じた損害
治療費、休業損害、入院慰謝料、通院慰謝料、後遺障害の慰謝料や逸失利益などが事故によって生じた損害として論じられる代表的なものです。不幸にして亡くなられるような事故では、生きていれば得られたであろう収入や、不慮の事故で急死したご本人の無念な思い、親族の嘆き悲しみに対する慰謝料などが請求できます。
なおこれらの問題を議論する上で医学、医療上の知識が大いに必要となってくる場合があるので弁護士はこの方面の研鑽も求められます。
以上が人身損害であり、これ以外にも車の修理費、代車料などの物的損害の請求が発生します。
交通事故による損害賠償請求のテーマには実に沢山の複雑な論点がありますので、事故に遭われた方は是非、弁護士に具体的なお尋ねをしてみて下さい。
(6) 損害を埋め合わす方法
損害の埋め合わせは加害者から支払ってもらうことが原則ですが、実際には自賠責保険、加害者の自動車保険、被害者の人身傷害補償保険、労働者災害補償保険(労災)、健康保険など、各種保険からの支払いが主となりますので、これらをどのような順序で活用していくかも大事です。
(7) 加害者の無保険、無資力、行方知れず
しかしながら加害者が自動車保険に加入していない無保険事故、加害者の無資力・行方知れずのようなケースもあり、このような場合は損害の回復が大変困難となります。
自賠責保険や人身傷害補償保険があれば、人身損害の最低限の支払いは受けられますが、しかし物損に対する支払いは受けられません。弁護士は手だてが尽きてしまい、依頼者の期待に応えられない悔しい思いをすることもあるのです。
3 ご相談の進行状況に関する典型的なケースのご紹介
交通事故案件の論点、争点は実に多方面にわたっており、弁護士にとって大変手強い分野ですが、しかし、通常のご相談では同じような問題点が繰り返し、検討されているのも実情です。次に典型的なものをご紹介します。
(1) 過失割合はどうなるか
事故の様子、事故を引き起こした不注意がどちらに、どの程度あったのか、これらについては常にといっていいほど厳しい対立が生じます。そのため、これらの点についてあくまで自説を貫くのであれば、損害賠償請求の訴訟を起こして裁判所に判断を委ねるほかない事例もでてきます。
決然と裁判を選択される方もいらっしゃいますが、多くの方々はできるだけ自説を貫いて有利な妥協の成立を弁護士に求めていらっしゃいます。適切な交渉と十分なご報告、さらなる打ち合わせを繰り返す中で妥協のご判断がつくと裁判を避けることが出来ます。
(2) むち打ち症(症状固定日は何時か)
むち打ち症のつらさを経験された方は大勢いらっしゃると思います。レントゲンなどの画像診断や神経学的検査では所見が見られないのに、ご本人は痺れ、痛み、だるさ、凝りなどに悩まされることは幾らでもあります。
このような場合に、ご本人の訴える諸症状が消えるまで、治療費と休業損害を払ってくれれば良いのですが、加害者が加入する保険会社では事故から3ヶ月を一つの目安として、その前後で症状固定扱いをする傾向があります。
症状固定とは、怪我が治癒したと判断され、あるいは、これ以上治療を続けても治療効果の上がる見込みがないと判断されることをいいます。原則として主治医の診断によりますが、時には保険会社が顧問医師の判断を根拠に、まだ主治医が症状固定と診断していないのに、治療費と休業損害の支払いを打ち切ってくることもあります。
症状固定の時期に争いがあれば最終的には裁判所に判断してもらうことになりますが、その前に心がけておくべきことがあります。きちんと継続的に医師にかかること、整骨院に通って病院に行かなかったとか、思い出したように時たましか医者に通わなかったなどは最悪です。整骨院に通うにしても医師に相談し、その必要性を分かってもらうことが大切です。
痛み、痺れ、だるさ、凝りなどの症状については、身体のどこの部位にそのような症状がでているか継続的に記録し、医師にもしっかり正確に伝えて下さい。私のところでは記録用のシートをお渡しして症状を記録していただき、症状が残る限り少しでも長く治療を続け、治療費と休業損害を払ってもらえるように工夫しています。
症状とその発現部位、これに対する治療などが一体として整合性、一貫性をもっていることが記録され、時間の経過とともに治療効果が現れていることなどが資料としてきちんと残ることが大切です。
それでも、むち打ち症の場合、症状が長く続き、治療効果が現れない期間も長くなると、どこかで症状固定と判定され、治療費と休業損害の打ち切りとなります。この場合、あとに残った症状が後遺障害として、別途、被害救済の対象になるかどうかが次の問題です。
(3) 残った症状は後遺障害に該当するか
症状固定と判定された時点でなお残っている症状が後遺障害に該当するか、するとして何級の何号に該当するか、これは診断書、レントゲンなどの画像や診療報酬明細書などをもとに損害保険料率算出機構で判定します。結果に納得できなければ異議申し立て制度もあります。
診断書がおざなりに書かれていると大変マイナスです。医師には、きちんと検査を行い、丹念に患者の訴える症状に耳を傾け、的確な診断書を作成していただけるように、弁護士が医師に連絡して医学上の見解をお聞きすることがあります。
(4) 整骨院での治療費は負担してもらえるか
まず、医師にきちんとかかることが大前提です。整骨院における治療のような東洋医学に基づく治療の有効性は、医師の治療(西洋医学)に比べて必ずしも確立されたものではないと考えられているため、医師からその必要性を認めてもらって整骨院にかかることが理想です。そうすれば整骨院の治療費も保険で払ってもらえますが、医師にかからず整骨院にだけかかっているようなケースですと、満足に治療費の支払いをしてもらえない危険が高いです。
(5) 休業損害、入通院慰謝料はどうなる
入院期間が休業損害や入院慰謝料の対象になることは問題ありませんが、通院の場合にどこまで休業損害や通院慰謝料が認められるか、これらは、先ほどご説明した症状固定日が何時になるかにかかってきます。
症状固定日が遅くなればなるほど休業損害、通院慰謝料の対象期間が長くなります。もっとも、症状固定日までの通院日数が少ないときは通院期間すべてが補償の対象期間になるわけではありません。ですから、過剰な通院はいけませんが、症状に応じてこまめに通院することは必要であり、横着は禁物です。
4 弁護士費用特約
加入している自動車保険の補償内容に弁護士費用特約がセットされている場合が多くなっていますので、ご確認下さい。この特約がついていれば、損害賠償請求を弁護士に依頼したときの弁護士費用が保険から支払われます。
保険限度額はおおむね300万円が一般的ですので、被害者が弁護士費用を自己負担するケースはほとんどなくなりました。但し加害者に対する請求額が高額に上るような重大事故で、解決に至るまでに相当の時間、手間、実費がかかるような困難な案件の場合は、まれに弁護士費用の自己負担が生じることもありますので、弁護士からよく説明を受けて下さい。
5 弁護士と依頼者の協力関係
交通事故に遭われた方は、怪我や車の破損で生活と仕事に大変な支障を受けます。そこで弁護士に相談となった場合でも、交渉に時間がかかり、はかばかしく進まないことがあります。
そうなると、依頼者は、心ない相手の不注意によって、こんなひどい目に遭いながら、何故、すぐに被害弁償がされないのか、相手は、事実ではない弁解をしているのに、自分の頼んだ弁護士は、どうして嘘を論破できないのか、等々、苛つかされることもあります。
こちらの請求を相手と相手保険会社が認めなければ話し合い解決はできません。非妥協的で変わった考えの持ち主が加害者だったような場合ですと、早期の円満な解決は弁護士の努力にも拘わらず困難となります。
そのような場合は、裁判を起こし、ご自分の主張が通るかどうか賭けてみることになります。損害賠償請求という権利行使も他の権利行使と同様、戦いであり、納得のためにどこまで戦うのかを判断する必要がでてきます。
依頼者と弁護士が一体となり、気持ちを通じ合わせて交渉を進めて行くことが何より必要で、それには弁護士からの十分な説明、依頼者からの適切な質問、そして遠慮のない率直な 意見交換が大切です。
ぎりぎりのところで妥協するのか、それとも妥協には納得できず裁判をするのか、しばしばこの決断を求められる局面に至ることがあります。裁判の見通し、裁判をすることの利害得失などについて弁護士から十分に説明をお聞きになってご判断ください。
良い解決には、ここまでご説明した交通事故損害賠償問題に対する依頼者の十分なご理解も大変重要となってきます。
|