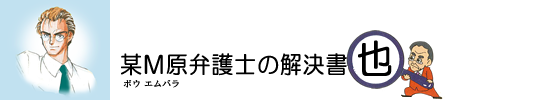
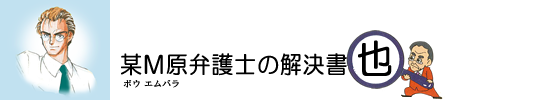
|
Top > 本文
1 はじめに
出産、手術、入院中の経過観察、通院中の経過観察、薬の副作用などをめぐる医療紛争、手術中の体位固定が原因で手足に神経症状が残った医療紛争、入院中の患者がベットから転落した医療紛争など、体験した医療紛争を思い出しただけでもその種類は様々です。
医療紛争は患者側にとって大変な事態であると同時に、非難の矛先が向く医師側にとっても身の細る思いの出来事です。
2 患者、家族と医師、病院側との感情的な対立
健康を損ねたり怪我をしたりで、医師の診断治療を受けるときには、患者は健康が回復し怪我が治ることを願い、すがるような思いで医師に我が身をまかせます。患者の家族も同様の思いで結果を待ちます。
それが不幸にして予期しない結果や悪い事態になった場合、患者や家族の驚きや落胆は大きく、何故こんな結果になってしまったのかと不信や不満が湧いてきます。
一方、医師側にとっても、患者を良くするために行った医療行為から不幸で悲惨な結果が発生したのですから、思わぬ事態の発生なのです。
彼らは、直ちに原因究明を行うと同時に、患者に対するこれからの医療行為をどのようにしたらよいのか、家族に対する説明を誰がどのように行うのか、などについて対処しなければなりません。
ここから患者側と医師、 病院側との医療事故に関するコミュニケーションが始まります。
患者側は、医師側に対して何故こんなことになってしまったのか説明を求めますが、実はその回答の前に是非とも欲しいのが、医師側からの「すみませんでした」、「もうしわけありませんでした」の一言なのです。
しかし医師側は、軽々しく責任を認めるような発言は控えようとして言葉を選び、用心深く会話を進めるので、患者側には到底誠実でオープンな説明には聞こえません。
患者側は、責任を認めようとせずに、事実の経過だけを説明する医師側の態度から、隠し事を疑い、責任逃れの都合の良い説明を聞かされている不快を感じ、それが怒りに変わっていきます。
患者側の医師側に対する質問は責任を認めさせようと次第に攻撃的になり、これを受けて医師側は軽々しく責任を認める発言はしない頑な態度をますます強めていきます。
その結果、話し合いの本来の目的であった原因の徹底解明や今後の医療行為をどうするのかなど大切な問題が置き去りにされ、非難と弁明の不毛な応酬になってしまいます。
全てがこのような経過をたどる訳ではありませんが、患者側と医師側との間の一般的な心理状態は概ねこのようなものです。
3 「すみませんでした」、「申し訳ありませんでした」の一言は禁句なのだろうか
医療事故にかかわらず、車の事故が典型例ですが、「謝ったら責任を認めたことになるから絶対に誤ってはいけない」とよく言われます。果たしてそうなのでしょうか。
医療事故で責任を問われるとすれば、刑事、民事、行政の責任です。
刑事で言えば業務上過失傷害罪だったり業務上過失致死罪であり、民事で言えば金銭の支払いを命ぜられる損害賠償責任であり、行政でいえば医師免許の停止や剥奪です。
「すみませんでした」とひとこと発言したら、これらの責任を認めたことになるかといえば、全くそうではありません。
これらの責任は医療行為の全体をつぶさに点検し、予期しなかった結果と医療行為との間に因果関係が存在し、かつ、医師や病院に過失があって初めて認められるものです。
彼らの責任問題は、医療行為の緻密な解明、分析による原因究明と、それに対する法的判断をまたなければ答えは出ません。
ですから、「すみませんでした」の一言と法律的な責任の発生とは別物であることを患者側も十分理解しておく必要があり、間違っても、「いま、すみませんでしたと責任を認めたではないか」などと攻撃して、医師側とのコミュニケーション不全を引き起こすことのないように冷静な対応が必要です。
患者側が医師側の謝罪の言葉にこだわり過ぎて、医療行為の詳細な解明や医療記録の十分な開示に支障が生ずることがあったらそれこそ本末転倒です。
では、「すみませんでした」の一言が如何なる意味なのかといえば、患者や家族の期待に添うことができず、思いがけない結果、深刻な事態になってしまったことに対する医師側の専門家としての悔しさ、つらさを表す言葉であり、患者と家族の驚きや不安、嘆きを自分達も同様に受けとめていますとの心情を表明する言葉です。
「すみませんでした」の一言が最初にあれば、患者や家族側は、驚きと不安で傷つけられた心が随分和らげられます。
医療事故の苦しみや痛みを医師側も共に分かちあってもらえるのか、それとも、自分達患者側だけで背負わなければならないのか、ここが、以後、患者側と医師側が充実したコミュニケーションを続けられるかどうかの別れ目です。
患者側の苦しみ、悲しみが理解できれば、「すみませんでした」、「申し訳ありませんでした」の言葉は、医学、医療のプロであればこそ自然に出るのではないでしょうか。
4 医師側から患者側に対する早期の、十分な説明が大切であること
医師側が、その医療機関に求められる医療水準にふさわしい診断、治療行為を行ったにもかかわらず、不幸な結果になった場合であれば、患者側はどれ程辛く悲しい結果であっても、医師や病院側を責め立てることは出来ません。
病気や怪我は医者にかかれば絶対に治る、絶対に助かるという絶対はありえません。
確かにこれは誰でも分かっているつもりなのですが、しかし実際の医療現場では、希望や期待に反する結果となってしまった場合、患者や家族側は、事情がわからないうちは医師側に対する不信が解けません。
医者や病院側は、患者に対し、一体どのような治療や手術、投薬をやってくれたのか。
患者の命を守り、状態の悪化を防ぐために、患者の全身状態の観察や管理をちゃんとやってくれたのだろうか。
医者や病院側は何か都合の悪いことを隠していないか。
患者側は医学や医療の事が分からず、つきっきりで患者を見ていたわけでもないので、分からないことだらけです。
それだけに真相を知りたいと思い、それが分からないうちは不信や不満が解けないのです。
速やかで、十分な説明が行われないと、患者側の疑心暗鬼は不信から怒りに変わり、医者側に対する責任追及という攻撃的な精神状態になっていきます。
ですから病院側から患者側に対する早期の十分な説明が何よりも必要なのです。
中には、結果が悪ければ、それはすべて医者や病院の責任であるといわんばかりの攻撃的な主張もあります。
家族や最愛の人が亡くなったり、状態が悪くなった場合、家族や関係者がこの事態をどうしても心の中に受け入れることができず、その辛さ、悲しさ、悔しさの感情が医者や病院に対するあくなき責任追及という攻撃的な行動に繋がることもあります。
時として患者側の不信感を取り除くことは困難をきわめます。
それは、医師や病院側が、これで良かろうと判断する説明の内容と、患者側が求める説明の内容とで大きな食い違いが生じていることも一因です。
ですから、医師や病院側は、どれほど大変ではあっても労を惜しまず丁寧な説明を繰り返すことが大切です。
5 医療訴訟を念頭においた患者側の準備
(1) 医療記録等の収集
医療事故が起きた場合、患者側は、先ず情報がなければどうにもなりません。ここでいう情報とは医師及び病院が作成したり収集した一切の医療記録です。
先ずこの医療記録の入手がスタートです。入手の方法はいろいろです。任意に提出してもらう場合もあれば、証拠保全という裁判所の手を借りて収集する場合もあります。
収集した医療記録が全てであるかどうか、時には怪しいことがありますので注意する必要があります。
最近は電子カルテが多くなっていますが、条件設定によって打ち出し記録の内容が異なりますので、この点も要注意です。
(2) 収集した医療記録の整理、検討
入手した医療記録の整理分析は弁護士にとって大仕事です。医療記録が入手できても医学、医療の知識がまったくないのでは、これらを整理分析することはできません。専門性を要求されるので、医療事故紛争を手がけない弁護士もいるくらいです。
(3) 協力医の確保
弁護士には医療や医学についてかなり勉強した方もおられます。中には医師免許を持った弁護士もおられます。しかし、ほとんどの弁護士は医学、医療の素人ですから、助言をしてくれるドクターを探して学習をしながら、自分で勉強して行かなければ、どうにもなりません。
(4) 原因と結果との因果関係・過失の構成
医者にかかってから深刻な事態を迎えるまでに時間の経過があり、この間にいろいろな診断治療がされているのが通常です。そこで助からなかったとか悪くなってしまったという不幸な結果をもたらした原因は何かを解明しなくてはなりません。
どの時点で、どのような診断治療をしていたら助かったのか(悪化を防ぐことができたのか)、または、どの時点の、どのような投薬や治療行為をしていなければ助かったのか(悪化を防ぐことができたのか)、をはっきりさせることが求められます。
ところが、このようなポイントを絞らず、入院から結果が悪くなるまでの全経過を取り上げて、医師や病院に過失があったと主張される例があります。このようなやり方はポイントのはっきりしない組み立てとして裁判所から嫌がられます。
裁判所は、何をしたことが(何をしなかったことが)問題なのか、その結果どうなったというのか、何をどうしていれば(何をしなければ)悪い結果が避けられたというのか、悪い結果の事態を避けることは可能だったのか、どのような注意を払っていれば避けられたのかを明確にするように求めてきます。
そこで弁護士は一連の経過のなかで、問題の核心を切り出して組み立て、問題とすべき原因と結果を明示し、同時に、医者や病院側の落ち度を明示します。
このような組み立てをして証明のテーマを明らかにしなければ、医師や病院の責任を問うことはできません。
診断治療や手術の結果が悪かった、悲惨な状態になっている、それなのに医師や病院側には納得できな言動がある、彼らに誠意が見えない、説明が十分ではない、といった不信や怒りだけでは、医師や病院の責任を問うことはできません。
厳密な組み立てと周到な証明が要求され、それに成功しなければ、どんな気の毒な結果であっても裁判で救済されることはありません。患者や家族の嘆きや悲しみ、怒りだけでは責任追及の材料にならないのです。
冷静に、忍耐強く、医学、医療という専門領域において、素人の患者側が医療専門家の反論に負けない議論、負けない証明をしなければなりません。
(5) 関係する医療文献の収集
原因と結果の間の因果関係や医師や病院側の落ち度を証明するために、関係する専門的な文献が必要になってきます。これらを探して入手するのも、大仕事です。
医療事故問題は資料収集などの仕事量が膨大となります。しかし、通常、弁護士は、一つの案件ごとに専念できる秘書や事務員を持っていませんので、依頼者側で弁護士と協議しながら資料収集に動ける人がいてくれると大助かりです。
(6) 損害の構成
医師や病院の責任を問う組み立てができたら、最後は、患者や家族の被った損害の計算とその証明の準備をします。身体障害を残したような場合、その証明と障害による終身の損害をどのように算出するか、十分な検討を要するところです。
(7) 弁護士任せにはしないことが望ましい
依頼者は弁護士に頼めば、何でもやってくれると期待したくなりますが、医療事故紛争は大変手のかかる事件なので、弁護士からすると、依頼者側で協力していただける方がいたら大助かりです。
また依頼者側は、素人とはいえ、関係する医学、医療の理解を深めながらことの推移を見守る必要があります。
これを怠ると、裁判そのものが、理解できないところに行ってしまい、不安ばかりが残り、それが時として依頼した弁護士に対する不信感にまで発展してしまう恐れもあります。依頼者は弁護士とともに学習を積み重ねていただきたいところです。
6 沸騰する患者側の心情とクールな裁判所の判断
悲劇的な事態を抱え込まされた患者側としては、納得のいく解決がなかなか得られないまま、時間ばかりが経過すると、医者や病院に対する怒りや憎しみが募る一方ですが、裁判そのものは、いたって淡々と進んでいきます。
医療事故裁判は、患者側の恨みつらみを晴らする劇的な場面があるわけではありません。忍耐強く、冷静に、弁護士と共に学習を深め、頑張る事が求められる実に辛抱のいる種類の裁判なのです。
しかし、親身になって一緒に頑張ってくれる頼りがいのある弁護士に行き当たれば、勇気と希望をもってつらい訴訟にも耐えられるはずです。
|