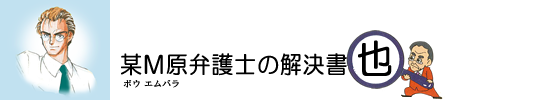
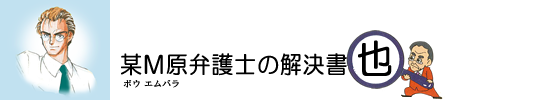
|
Top > 本文
工場の譲渡、10数店舗のレストランを一括した譲渡、何十件もの経営に行き詰まった温泉ホテルや旅館の事業再生や会社自体を丸ごと売買する案件などを体験して、これらのケースに共通して思うことが一つあります。
資金が回っていることと、利益の出る健全な事業を行っていることとは全く別のことであり、資金繰りが尽きてしまうまで見境なく事業継続に拘ることは経営者として最悪の選択だという現実です。
1 事業というもの
工場やレストラン、温泉ホテルをイメージして頂ければ、すぐわかることですが、事業とは、建物、設備、技術、従業員、仕入先、販売先、そして取引実績や信用などが一体として結びついた装置に、資金という血液を注入し、経営者から従業員に至る人々が、経営、運営、企画、開発、営業といった知恵と努力でこの装置を動かすことで製品やサービスを生み出して販売し、その収入で人件費や仕入代金などの装置を動かすために必要となった支払いを行い、最後に手元に残る利益の最大化を目指す営みといえます。
こうしてみると事業とは、社長や社員あるいは仕入れ先や顧客といった個々の人々から独立して存在する一つの社会的な生き物であり、雇用を生み出し、製品やサービスという社会的な価値を創造する極めて大切な社会的財産であることがわかります。
ですから事業は守り通さなければならず、現経営者が守り通せなくなった場合は、経営者の選手交代をしてでも事業を守り通すことが求められます。
だからこそ、ここに事業譲渡という発想が出てくるのです。
2 色々な事業譲渡
いままでの事業拡大路線から、選択と集中による経営資源の有効な投資に会社の方針を転換し、不採算部門や今後の事業展開の上で整理したほうがよい部門を事業譲渡することで本体事業から切り離し、残した本体事業に専念してその強化を図ることがあります(譲渡をする方の会社の戦略)。
また、会社の競争力を強化するために事業譲渡をうけ、人、物、取引先、技術、信用力などを迅速、効率的に取り込むやり方もあります(譲渡を受ける方の会社の戦略)。
さらに、会社の倒産整理にあたり、収益力を持った部門があれば、その部門だけを切り出して事業譲渡することにより、譲渡をする方では債務弁済の原資を生みだし、譲渡を受ける方では社会的財産といえる事業を再生するやり方があります。
3 生き続ける事業部門
事業という社会的な生き物の健康状態は色々な観点から診断できますが、単純でわかりやすい見方をすれば、今現在、利益が出ているか、資金が回っているか、将来的にも利益が出るか、資金が回るかの分析判断に尽きます。
緻密で周到な分析結果からイエスの答えがでれば、その事業は考え抜かれ、十分に手を打って運営されている健全な事業です。
しかし、今現在は何とかやりくり算段して資金が回っているが、利益が出ていないとか、仮に利益が出ても債務超過状態のため資金繰りがどんどん圧迫されてしまうなどの困った状態にあれば、社会的な生き物としての事業は既に病気状態です。
病気状態を改善する見込みが立たないという最悪の状況に行き詰まれば外科的な荒療治が必要であり、このような最悪の状況の中での最善の治療方法が事業譲渡といえます(尤も、この治療方法が取れない程に事業が劣化している場合も多くあります)。
収益を生み出している事業部門(改善によって収益を生み出す可能性がある事業部門を含みます)は、経営状態が悪化の一途を辿る事業本体から切り離してこれを他へ譲渡し、新たな経営主体によって資金を投入し、適切な経営を行っていけば、再生の可能性があります。
事業譲渡の手法によって、社会的な生き物である事業を生き返らせ、雇用と仕入先、取引先を守り、製品やサービスを生み出し続けさせ、社会に貢献することが可能となります。
4 事業譲渡する側の勇気ある決断
今現在なんとか資金繰りができていても、収益が上がっているか、仮にそうではないとしても工夫と努力次第で収益の上がる構造に改善する余地があるか、この点の見極めは何より大切です。
無理な資金繰り(その典型は見境のない借金であり、無計画な資産の売却です)で事業の継続を維持できていても、その事業が赤字状態であり、黒字に転換できる見込みがないとしたら、つぎ込む資金は倒産を先送りする時間稼ぎをするだけの無駄な経費にすぎません。
時間稼ぎにより事業再生の可能性は遠のくばかりで何も良いことはありません。苦しみ悩む時間がそれだけ長くなり、再生の見込みがある事業でも劣化が進行して価値を失い、関係者にかける迷惑は大きくなるばかりです。
赤字続きのため、或いは黒字が出ていても累積赤字のために、いずれ資金ショートを起こすことが避けられないと判断したら(実はこの判断が大変難しく、何とかならないか、何とかなって欲しいと根拠もない願望にすがって現実を直視しない経営者が沢山おられます)、勇気を持って、事業の手仕舞いや事業譲渡を考えるべきです。
事業譲渡について大切なことは、ひとえに譲渡側の経営者の勇気ある決断です。
事業譲渡は、譲渡する側からいえば事業の整理であり手仕舞いです。したがいまして、事業譲渡の後には債務整理という辛い後始末が残ります。
これからの生活はどうなってしまうだろうか、債権者からどのような仕打ちを受けるだろうか、連帯保証人になっていただいた方々にかける迷惑、世間からの冷ややかな目などを想像すると、経営者は恐怖と絶望で、とても手仕舞に踏み切る決断ができません(経営者の悩みと苦しみについては、別稿の「会社の行き詰まり」をお読み下さい)。
こうして決断ができないままに無為な日々を過ごすうちに事業は急速に劣化し、社会的な財産である事業はすべて駄目になってしまいます。
ホテルやレストランはただの箱となり、工場は鉄くずの塊同然、雨ざらしの廃屋となってしまいます。
この最悪の事態を回避できるただ一つの道は、経営者の勇気ある決断なのです。
5 事業譲渡を受ける側の目利き
業容を発展強化する上で、事業譲渡はもっとも効果的な手法の一つといえます。
どの業界でも競争力強化のためのM&Aや事業譲渡が日常的に行われています。
しかし一方、傘下に収めようとする事業の評価を誤ると、とんでもない負担を背負い本体事業の足かせになってしまいます。ですから事業譲渡を受ける側も簡単ではありません。
先程、1項で事業について述べました。ここでもう一度、繰り返します。
「事業とは、建物、設備、技術、従業員、仕入先、販売先、そして取引実績や信用などが一体として結びついた装置に、資金という血液を注入し、経営者から従業員に至る人々が、経営、運営、企画、開発、営業といった知恵と努力でこの装置を動かすことで製品やサービスを生み出して販売し、その収入で人件費や仕入代などの装置を動かすために必要となった支払いをし、最後に手元に残る利益の最大化を目指す営みといえます。」
事業譲渡を受けるとはこのように複雑な装置を購入することですから目配り、気配りをし、検討を要する対象も自ずと複雑になります。簡単にみても次のような点を気にしなければなりません。
(1) 譲渡の対象は何であるのか。事業と一口にいってもその中身にはいろいろなものがあるので、予定通り過不足なく譲渡を受けると共に、不必要なものや有害なものはくっついてきて欲しくないのです。
(2) 必要な役所関係の手続きは何か。
(3) 譲渡金額は幾らか、その金額は妥当か。支払い方法はどうなるのか。
(4) 事業譲渡を受けた後に、さらに予想外の出費を必要とされるリスクはないか。
(5) 譲り受けた事業の今後の経営、運営が予定通り進められるか。予想したように上手く行かず、お荷物になるようなリスクはないか。
事業は色々な要素が組み合わさった装置であり、事業譲渡とはそれを丸ごと買うことです。
しかし丸ごと買うといっても、その手続まで丸ごと一遍に終わる訳ではなく、その中身の点検や確認、人や物や取引先の承継に伴う諸手続き、役所対応など大変煩雑な作業を行わなければなりません。どうしても専門家の手が必要となってきます。
今後のために必要な社員は辞めずにいてくれるのか、必要のない社員は引き取らなくてすむのか。
今後のために必要な取引先や仕入先は今まで通りの関係を継続してくれるか、企画、開発、技術力、営業力といったマンパワーは見込み通り発揮されるだろうか。
引き継ぐ不動産、在庫、売掛金などの評価は大丈夫だろうか、帳簿に上がっていない債務があって後日請求が飛んできやしないか、承継する事業に関連する法的トラブルはないか等々、譲渡を受ける事業それ自体の金銭評価をするにあたって不安要素は山ほどあります。
また、譲渡に不満な債権者から反発が出て裁判紛争になったり、元の従業員から雇用の継続を主張されて労働紛争になったり、譲渡を受けた建物設備などの老朽化は想像以上に激しく想定外の改修費用が必要となってしまうなど、事業譲渡を受ける側にとって予測できないことや、予測を誤ってしまうような事も起きる可能性があります。
このように分からないことだらけなので、事業譲渡を受けようと考える場合には、傘下に収めようと計画している事業について経営コンサルタント、公認会計士、弁護士などによる業務・財務・法務などの観点から周到な調査分析が必要となります。
これをデューデリジェンスといって、専門に行う会社も沢山あり、費用も相当かかります。
それにしても、様々な調査分析資料が上がってきたら、それらを読みこなして消化し、最後は自分達で見通しを立てて判断をしなければなりません。
このように専門家などの手を借りていろいろ複雑な手順や分析、検討が必要ですが、それにしても最後に必要なのは事業譲渡を受ける側の目利きの力です。
このように事業を譲り受けることは一筋縄ではいきませんが、しかし、事業譲渡が本業発展の有力な手段である以上、経営者としてその研究を怠ることは出来ません。
|