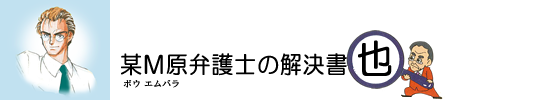
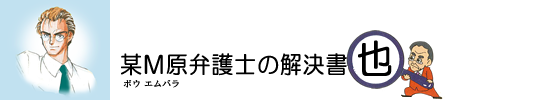
|
Top > 本文
1 遺言能力という考え方
高齢者の作成した遺言公正証書が、その作成当時、本人には遺言能力があったとは認められないとの理由で、裁判所から無効と判断される例が珍しくなくなりました。ここで言われる遺言能力とは、理解力、記憶力、思考力、判断力、表現力などの精神作用が適正に働いて、ご本人の最終意思の表現として尊重されるべき遺言書を作成出来る状態のことです。
2 法的に有効な遺言とはいえないケース
一つの例をご紹介します。
遺言書を残したご本人は、その作成当時、もはや自分の所有している財産の内容もはっきり記憶出来ていなければ、どのような理由で、誰に、何を分け与えるのかを考えたり判断出来る状態にもなく、そればかりか、ずっと以前に亡くなっている筈の夫が夕べやってきたとか、話をして帰ったなどと明らかにおかしな発言をする有様でした。
遺言者は高齢で認知症が相当に進んでいました。その様子は入所していた施設の生活医療記録や介護認定記録からも窺えました。ご本人は遺言書に書かれている内容を理解できていたとは思えませんでした。ましてや遺言書に書かれている内容を公証人に口頭で述べることなど出来る筈もなかったのです。
このような精神状態、健康状態の人が遺言公正証書を作成しても、書かれている内容通りの相続を認めることは、もはやご本人(遺言者)の望んだ結果の実現とは言えません。公証人が作成し、弁護士が証人となっていた遺言公正証書でしたが、裁判所は無効とし、その判決は確定しました。
3 遺言制度の趣旨
遺言制度はご本人の最終意思を尊重し、これを実現しようとする制度ですが、先ほどのような精神状態、健康状態のもとで作成された遺言書では、その内容をご本人の最終意思として尊重し、その実現を図ることは望ましくありません。
このような精神状態、健康状態のご本人(遺言者)が遺言公正証書を作成することには元々無理があったのですが、その無理を押してでも遺言公正証書を作りたい人が周囲にいると、かかる事態が起き、将来の紛争へとつながって行くのです。
4 法律家が関与しても遺言が無効となるケース
さて、遺言公正証書は、公証人という法律専門家が作成するものですから、遺言能力が認められないとして、後日、裁判所から無効と言われてしまうような事態は考えられないように思いますが、実はそうではないのです。
その理由は、認知症にかかった高齢者について、どの程度の症状に止まっていれば自己決定権を尊重し、どこまで症状が進行したら本人保護のため自己決定権よりも周囲からの支援を優先させるべきか、その境目を画一的に判断できない微妙な問題があるからなのです。
遺言の有効性を巡る紛争を予防するには、遺言書を作成する前に、ご本人に医師の診察を受けていただくことです。ご本人が遺言のなんたるかを理解し、自分が把握している所有財産の死後における承継について、誰にどのような分け方をするかを考え判断できる精神的な健康を保持していると、診断書に書いてもらえれば安心です。
5 遺産相続の前哨戦たる遺言書の作成
同居している子供が先々を心配して、認知能力の低下が始まった親に遺言書を書いてもらうケースは時折見られます。しかし親の死後、自分に不利な到底納得できない遺言書がでてきて、しかもその作成当時、親には既に認知症の状態が見られていたとなれば不満な兄弟姉妹が黙っていません。かくして遺言書の作成は相続紛争の前哨戦となり、子供たちは誰かが自分に都合のいい遺言書を親に作らせないかと互いに疑心暗鬼になって、親の生きている間から将来の相続を巡る紛争勃発につながります。どうしたらこのような紛争を予防できるのかが相続紛争前哨戦における法律相談ですが頭を悩ませます。
|