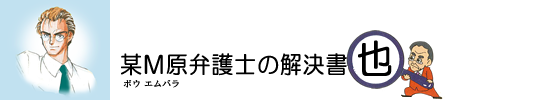
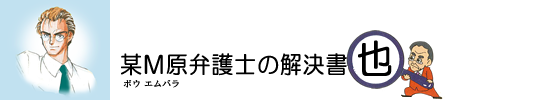
|
Top > 本文
1 はじめに(話し相手、聞いてくれる人の重要性)
離婚すべきかどうかの判断は実に難しく困難です。不幸にしてこの問題に直面してしまった方の中には、悩みの深さから、かなり心が打ちひしがれてしまい健康を害した方もお見受けします。
お気の毒な例では心療内科に通い、抗うつ剤などの抗精神病薬を服薬されている例もあります。このように深刻な精神状態に陥った相談者が、弁護士に相談することは、苦境を脱出するための、最後のチャレンジに近いものがあります。
それだけに弁護士に対する期待度は大きいので、相談を担当する弁護士は大変気をつかいます。
離婚の法律相談では通常これから述べる2から8までの離婚メニューが説明されますが、このように心にダメージを受けてしまった相談者にはもっと大切なことがあります。
それは相談者が結婚してからこれまでの長い間に味わってきた、辛く悲しい生活の悲惨な様子を弁護士が真摯にお聞きすることそれ自体です。
相談者が弁護士との会話を通じて、ご自分の感情や気持ちの混乱を和らげ、元気と勇気を回復し、自ら進むべき方向を見つけ出せるようになるかどうか、これこそが離婚相談の入り口にあたって最大の課題です。
離婚をするべきかどうか迷っている方、離婚を決断してはみたものの経済的なことを含めて将来の不安が大きいため、離婚に踏み出せないでいる方、反省や後悔が行き過ぎて自己否定の塊となり、精神的なブラックホールに落ち込んで苦悩している方、いろいろなタイプの相談者がおられます。
繰り返しになりますが、このような方々にとって最も重要なことは、アリ地獄のような悩みの淵から這い上がり、自分の進むべき方向性をしっかりと見つけ出し、現実の一歩を踏み出す元気と勇気を取り戻すきっかけを掴む事であり、それからでないと、これからのご説明が活かされません。
離婚の法律相談で出会った弁護士が、自分に共感し、自分と一緒に憤り、共に悩んで考えてくれる理解者であると感じることが出来た時に、相談者は初めて、元気と勇気を回復するきっかけが掴めるように思います。
離婚ができるかどうか、慰謝料は幾ら支払ってもらえるのか、財産分与はどうなるのか、親権は取れるかどうか、などの話はそれから後のことです。先ず自信を持って直面する問題を冷静周到に考え、これからの自分の人生に対する答えが出せる元気や勇気を回復できたかどうかこそが一番大切な事です。
しかし、このような弁護士の熱心な対応には、時として、とても大きな危険が伴います。なぜなら相談者に誤解を与えたり、弁護士に対する依存心を強めさせてしまう弊害があるからです。
このような誤りや失敗をしないためには、弁護士は、相談者の心の闇に踏み込まないで離婚メニューの説明に徹し、「離婚の意志が固まったら、また相談に来てください」と答えて相談を終えることが一番無難です。
しかし、堂々巡りの話しになりますが、これでは相談者の満足や納得が得られず、相談者は来たときと同じ暗い顔で法律事務所を出て行くことになりかねません。何とか力になりたいと願っていた弁護士にとって誠に辛く、無力を感じる瞬間です。
相談者は、弁護士から、心の闇に踏み込んだ聴き取りや助言をしてもらって自主自立の勇気や元気を回復できた、しかし決して弁護士の話に甘えや誤解をする弱さに陥ることはなかった、このような離婚法律相談の実現が理想です。
以下では離婚の交渉で協議される項目(メニュー)を順次、ご説明します。
2 財産分与の請求
(1) 清算的財産分与
結婚してから別居に至るまでの間、夫婦が協力して稼ぎ出し、蓄積した財産(大抵の場合は夫名義となっていると思いますが)、この財産を分割することを清算的財産分与といいます。
(2) 退職金も財産分与の対象になります
夫婦は平等ということで、分割割合の原則は2分の1です。財産分与の対象となる財産の範囲や種類について、結構もめる事がありますが、ひとつ知っておいて頂きたいのは、夫の退職金(妻の退職金という例もあるでしょうが、通常の場合を想定しました)が財産分与の対象になりうることです。
熟年離婚の男性にとっては困ったことですが、妻にとっては天与の助けです。退職金は本当にもらえるのか(途中で会社が倒産してしまうような例もあります)、幾らもらえるのか、これらは退職金を現実にもらってみなければ分かりません。
しかし、裁判所は、退職金の支給が将来ほぼ確実であると判断すれば、退職金の分割を認めます。但しどのような計算で分割金額を認めるのか、支払い時期をいつにするのかについては色々な取り扱いがあります。
いま退職した場合に、幾らの退職金が支払われるか会社に算出してもらい、その金額を基準にして夫に支払いを命ずる解決がされることもあります。
(3) 扶養的財産分与
子供たちの教育費や家庭の生活費にお金がかかり、まだ夫の貯蓄はゼロ状態に近く、しかもマンションの価値を上回る多額の住宅ローンが残っているような場合でも、夫はこれから10年以上にわたって高額な給料とボーナスを手にして最終的には相応の貯蓄ができると期待できる場合、今は分与できる財産がないので財産分与請求には応じられませんよという考え方が通用するのでは、経済的に無力な妻が気の毒です。
そこで、このような経済的な基盤のない妻の離婚後の生活に対する配慮として財産分与が認められる場合もあります。これを扶養的財産分与といいますが、裁判所の判断は清算的財産分与よりも厳しそうです。
3 慰謝料の請求
(1) 結婚生活を破綻させた者は誰か
結婚生活を続けていくことが出来なくなった原因を作った夫または妻が、結婚生活の被害者である相手方に支払う金銭を慰謝料といいます。
夫婦のどちらが悪かったから結婚生活がやって行かれなくなったのか、この点は常に大論争となります。例えば夫の不倫が見つかって離婚騒ぎとなった場合でさえ、夫は妻の悪口を言いたて、妻が悪かったから出来心の不倫をしてしまったなどと弁解してくることはザラです(勿論、逆のケースもあります)。
金銭感覚、夫婦親子関係のあり方、生活スタイルの相違などが原因となって結婚生活がうまく行かなくなった場合、すなわち性格の不一致、相性の悪さ、もっと言えばお互い様でしょ、とひとくくりにされてしまうような夫婦のいさかいでは、なかなか慰謝料は認められません。
慰謝料が認められるためには、暴力、生活費を入れない、家に帰ってこない、精神的に相手を追いつめて心身症状態にしてしまった等、余りにひど過ぎる、激しく一方的で自己中心的過ぎる、性格が違うからといってそこまで相手を苛めなくてよいではないか、このような心証を裁判所に与えられるだけの具体的な事実を揃えて証明する必要があります。
そこで弁護士は、2人が交際を始めたときまで遡り、時にはお互いが育った生育環境まで遡って、いろいろな事を聞き出し、それを時系列表にまとめて分析します。そして、ああでもない、こうでもないと懸命に考え、依頼者の苦労を理解し、それを言葉に表現しようと努めるのです。
(2) 慰謝料の金額
慰謝料問題では、当然のことですが金額が気になります。一言で申しますと、酷い目にあったので相手に慰謝料を払わせなければ気が収まらないと怒っておられる夫、または妻にとって、納得できる額の慰謝料が認められることは難しいのが実感です。
その理由は、慰謝料全般に言えることですが、裁判所の認める慰謝料のレートが我々の生活感覚からするとかなり低いからです(目に見えず、人によっても異なる心の傷を損害として認定し、これを金銭に見積もって、強制的に相手方に支払わせることに、裁判所は慎重にならざるを得ないのかも知れません。)。
結婚生活の継続を不可能にした出来事の数々、結婚生活の期間の長さ、配偶者の収入額などが参考にされますが、極めて大雑把に離婚慰謝料の相場をいえば、300万円を基準にしてその上または下といったところですが、300万円の慰謝料を認めてもらうためには相当な工夫と努力が必要です。
慰謝料が500万だとか1,000万になるケースは大変稀であり、よほど長期間にわたって酷く苦しめられ、肉体または精神に障害(傷害)が残る程の苦痛を味わったとか、相手の収入が高額であったりした場合に限られます。まして、1,000万を超えるような慰謝料ともなれば、なくはありませんが、極々稀です。
相手が早期の離婚を願い、ある程度の金額の慰謝料を支払ってでも急いで離婚したいと希望するようなケースであれば、多めの慰謝料支払いが期待できます。しかし、早い離婚を希望しながらも、その一方で慰謝料の支払いとなると気前のいい金額提示がされないのが通常の例です。
4 婚姻費用の請求
(1) 兵糧攻め
離婚騒動が始まり、別居状態となっているような場合、しばしば夫が生活費を減らしたり、入れなくなって兵糧攻めをしてくることがあります。これでは離婚戦争を戦えません。
離婚が成立するまでは、生活を支えている配偶者(通常の場合は夫)は家庭生活に必要な費用を負担する義務があります。仮に別居状態となっていたとしても、原則としてこのことに変わりはありません。
(2) 婚姻費用の請求方法と算出方法
生活費の確保のため裁判所に手続をとって離婚までの婚姻費用の支払を命じてもらう方法があります。
婚姻費用の算出については、裁判所で広く使用されている算定表があります。夫と妻の収入が分かれば機械的に金額(但し上限と下限の幅をもった金額です)が計算できます。
この算定表による金額は、今まで家庭の生活費にかけられた金額よりも低い額となりがちです。収入が増えるわけではないのに、別居で世帯が二つになって生活にかかる費用が増えてしまうので、どうしても今までよりお金が不自由になることが避けられません。
(3) 過去の婚姻費用の請求
配偶者が婚姻費用を入れてくれないために自分が生活費を全面的に負担してきた場合は、過去の婚姻費用を請求する方法があります。
もっとも、さかのぼる期間が長くなると、裁判所は思うような過去の婚姻費用を認めてくれません。ですから兵糧攻めにあったらすぐに婚姻費用の請求をしましょう。
(4) 給料の差押え
裁判所から命ぜられても婚姻費用を支払わない配偶者がいます。その場合は、給料を差し押さえるのが典型的な対向手段です。
5 子供の養育費の請求
(1) 親の義務
両親が子供を養育する義務を負っていることは改めて説明を受けなくても理解できるところです。家庭生活を支えている配偶者(通常の場合は夫)は子供の養育費を負担する義務があります。
離婚騒動になりますと、子供の生活をみている配偶者(通常は母)に対し、夫が相手方を追いつめたり、自分の言い分を通す目的で養育費を払わなかったり減らしてくることがあるので、その時は、母親が夫に対し子供の養育費を請求することになります。
(2) 養育費の算出
子供の養育費は裁判所が広く用いている算定表で算出されます。夫と妻の収入が分かれば機械的に金額(但し上限と下限の幅をもった金額です)が計算できます。
婚姻費用のところで述べたのと同じ理由で、現実に必要となる金額よりも低い額となっています。裁判所に訴えて請求できる点も婚姻費用の請求と同様です。
6 年金分割
(1) 分割が必要な場合、所定の事務手続きが必要です
離婚に伴って妻が(夫がという場合もありますが、稀なので、妻が分割を受ける場合を前提に説明します)年金分割を受けられることはかなり広く知れわたっています。
但し年金分割を受けるためには所定の合意をするか、裁判所に決めてもらいその後、社会保険事務所で所定の手続きをする必要があります。
(2) 年金分割の割合
法が定める年金分割の割合の上限は2分の1であり、実務の運用も2分の1とされているのが実情です。ここにも夫婦平等の考え方が現れています。
(3) 単純な現金の分割ではありません
しかし、誤解をなさらないでください。夫が受け取る年金の半分を妻が受け取れるという意味ではありません。
正しくは、年金分割の対象期間(婚姻期間等)に夫が納付した保険料の一定割合を妻が納付したものとして記録を付け替え、これをもとに妻の年金給付金額を算定するというものです。
少々ややこしいので社会保険事務所にお尋ねください。
7 親権者・監護権者
(1) 子供が最大の被害者
離婚は夫婦にとっては互いの問題ですが、子供にとっては降って湧いた災厄であり最大の被害者は子供です。両親が離婚して他人となり、別々に暮らすようになると、子供たちはどちらかの世帯に身を寄せなければなりません。
離婚をするような事態ですから、離婚後に元夫婦が子供の養育や財産管理(子供に財産があるケースは稀ですが)を巡って円滑な話し合いが出来るかどうか危惧されます。
そこで、法律は、子供の身の上に関する判断は父母のどちらか一方に任せ、他方には口を挟ませないようにしています(もっともこのような考え方自体、最近では批判を受け、法改正を目指す動きがあります)。
(2) 親権者の「権」は権利を意味するものではない
子供の健やかな育成と子供の財産管理(子が財産を持つことは稀ですが)のために必要な判断や決定をする責任者を親権者といいます。
「親権者」という言葉には権利の「権」の文字がついていますので、親の権利のように聞こえてしまいますが、子供の健やかな育成に携わらなければならない責任であって、権利ではなく義務と申しておきたいところです。
親権は、これを持たないもう一方の親が子供の問題に口を挟むことを排除出来るという意味では、権利と言えるかも知れませんが、いずれにしても、親権者の利益や感情を実現する性質のものではありません。
(3) 親権の内容、監護権者の意味
親権の項目としては、懲戒(いわゆる愛の鞭を振るうことですが、程度やしかり方が難しいです)、子供の職業許可をする、15歳未満の子供の養子縁組を承諾する、15歳未満の子供の氏の変更手続きを代理する、子供に財産があればその管理をするなどが挙げられます。
監護権者とは子供と同居して共に生活する親のことです。法律は親権者と監護権者を一体とすることを原則としています(この考え方に批判のあることは先に述べた通りです)。
(4) 子供中心に考えることの重要性
離婚にあたって、父母のいずれが親権者、監護権者となるかをめぐり激しく争われ、そのため離婚の成立に時間のかかる事例(夫婦共に離婚することに異存はないが、親権者と監護権者を何れにするかが決まらないため)がよく見られます。
離婚に直面した夫婦の多くが、互いに、親権が欲しいという言い方をされます。子供が可愛い、相手に子供を任せたらきちんと教育しつけがされない、憎き相手に子供を渡せるものか等、なかなか難しい要素が絡みます。
ややもすると子供が「もの」扱いされているように見えるケースもあります(ご本人達にはそんなつもりはないのでしょうが)。ここで大切なことは、あくまでも子供中心に考えなくてはならないということです。
別れて他人となる両親のいずれと生活することが子供にとってベターなのか(ここではベストということはあり得ません)、この観点から判断されなければなりません。
裁判所の原則的取扱は親権者、監護権者共に母親とすることであり、その結果が明らかに子供のためにならないとか、子供たちは父親と同居した方が良いという根拠が証明されない限り、この判断は変わりません。
8 面会交流
(1) 面会交流の趣旨
離婚によって子供と別れることになった父親、または母親は子供と会える機会を求めます。
また親の離婚によってどちらか一方の親と引き離されてしまった子供達にとっても、一緒に生活できなくなった父親または母親と会いたく思うことがあります。
これは親子の情としても当然であり、子供の精神的な発達にとっても大事です。従って離婚によって別居することになった親と子供たちの交流は尊重されなければなりません。この交流のことを面会交流といいます。
(2) 面会交流の内容
子供の日常生活を最優先しながら、それを妨げないように、また子供たちの負担にならないように、いろいろ配慮してルールが決められて実行されます。
ごく一般的に言えば、毎月1回程度、場所を決めて、親と子供が数時間一緒に過ごします。夏休み、冬休み、時にはクリスマスや正月の行事、誕生日なども視野において、日頃別居している親と子供達との宿泊を伴う交流の機会が計画されます。
また、運動会や学芸会など学校行事にも出来るだけ顔を出してもらうように配慮します。
(3) 離婚した元夫婦の親としての協力関係
以上のような面会交流が円滑に実現できるかどうかは、ひとえに離婚した元夫婦である両親の寛容な精神と協力関係の有無にかかっています。子供がいる限り、離婚した元夫婦は、決して完全な赤の他人というわけにはいかないのです。
と、ここまでは理想論を述べましたが、ドメスティックバイオレンスが原因で離婚したような場合であれば、子供達は別居状態となった親と会いたいとは思いません。
子供の心理は大変微妙、不安定であり、周囲の様子を気にかけて本音と異なる発言をしたり、厳しい親を嫌い甘やかす親になつくなどして、円滑な面会交流に波風をたてる原因をつくることもあります。
このような場合こそ周りの大人には冷静で子供の心理と感情をよく踏まえた対応が求められます。表面的な子供の言動に動かされて極端から極端に走らないことが肝心です。
離婚によって子供と別居状態になった親にとり面会交流は大変こだわりたくなる問題ですが、時には、何の障害もないのに、離婚後、子供の前にまったく姿を見せなくなる親もいます。
また極端な場合ですが、面会交流を請求しないと約束する離婚夫婦も稀にあります。
かくして離婚後の親子関係は実に様々ですが、離婚した元夫婦である両親は、離婚してしまった親として自分が子供たちに何をするべきなのかを考え続けて欲しいです。
|